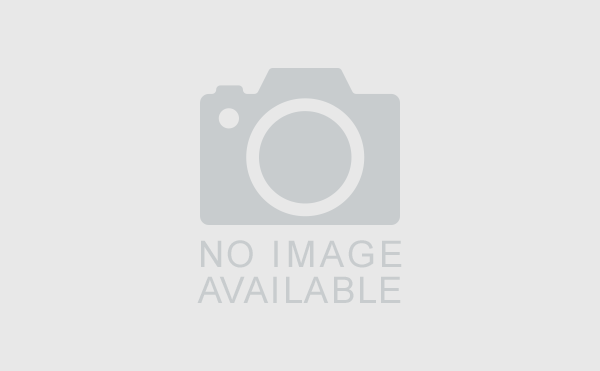明日からすぐ使える!身体の評価(肩甲骨)
セラピスト養成スクールCEOL Academy JAPAN認定講師の河野真奈です。
身体の評価「骨盤編」は読んでいただけましたでしょうか?
今回は「肩甲骨」です!肩甲骨は唯一宙に浮いている骨として、支えている周りの筋肉の影響をもろに受け簡単に位置は動きます。
日常のアンバランスな身体の使い癖で肩甲骨の位置が良くないところで固定されてしまうと肩周りの動きにも支障が出て万年肩こりさんの出来上がりです。
「肩甲骨」の評価ができるようになると効率よく肩周りや背中の筋肉を緩めることができるようになりますよ^^
評価方法を覚えるのではなく、”なぜ”そこを見るのか?の”なぜ”を大切にしてくださいね。
肩甲骨の動き
肩甲骨は肋骨の上にペタンと乗っているだけでいろんな方向にスライドするようにして動きます。
動きの種類は6種類。
- 挙上
- 下制
- 内転
- 外転
- 上方回旋
- 下方回旋
このうち今回は「内転」「外転」について見ていきます。
肩甲骨の評価(内転・外転)
内転・外転は左右の動きに関わります。
背骨と肩甲骨の間の間隔が極端に狭い(中央に寄っている)状態を内転。
背骨と肩甲骨の間の間隔が極端に広い状態を外転といいまうす。
だいたい、背骨と肩甲骨の間隔は指3~4本が標準です。
では肩甲骨内転・外転が分かったらセラピストの私たちが気を付けるべきことは何なのか?
肩甲骨内転・外転に関わっている筋肉は?
肩甲骨内転に関わる筋肉
- 菱形筋:肩甲骨を内側に引き寄せ、安定性をサポート。
- 僧帽筋中部繊維:肩甲骨を内側に引く主役の筋肉。
肩甲骨外転に関わる筋肉
- 前鋸筋:肩甲骨を外側に引き、胸郭に固定する。
- 僧帽筋上部繊維:肩甲骨の動きを補助する。
これらの筋肉が伸びたり縮んだりすることで肩甲骨は内転したり外転します。
肩甲骨の動きが悪くなる原因
- 長時間の同じ姿勢(デスクワークやスマホ操作)
→ 肩甲骨が前方に引っ張られ、巻き肩の状態、肩甲骨が外転の状態で固定される。 - 筋力のアンバランス
→ 菱形筋や僧帽筋中部繊維が弱化し、肩甲骨が安定しない。 - 姿勢不良
→ 猫背や巻き肩で筋肉の機能が低下する。 - ストレスや呼吸の浅さ
→ 肋骨と肩甲骨の連携がとれなくなる。
肩甲骨内転・外転でセラピストが気を付けるべきことは?
筋肉は伸びているところがあれば縮んでいるところが必ず対になって存在します。
コリや痛みは伸びている筋肉上で感じやすいので、セラピストはそこをもみほぐさなきゃ!となりがちですがそれが落とし穴なんです。
伸びているところは、もうこれ以上伸びたら切れちゃうよ!やめて!というSOSを痛みという形で私たちに教えてくれます。
そこをほぐすということは柔らかくしてさらに伸びやすい状態を作っているということです。やりたいことは逆のはずですよね!
私たちセラピストが緩めるべきは縮んでいる方の筋肉なんです。
だから肩こりと聞くと「菱形筋」のあたりもごりごりやりたくなりますが、肩甲骨外転のお客様の場合は菱形筋はそこまでほぐす必要がありません。
やりすぎると逆効果になってしまうということをセラピストの皆さんは知っておいてください。
肩甲骨外転が強い方には「前鋸筋」や「僧帽筋上部線維」、深層には「肩甲挙筋」(肩甲骨の挙上に関わる筋肉)という筋肉があります。
この辺りを丁寧にほぐすと良いですね^^
やり方や答えを暗記するのではなく、お客様の姿勢や普段のライフスタイルを元に、どの筋肉が伸びていてその筋肉が縮んでいるのかをかんがえる癖をつけましょう!!
どんなお客様にも臨機応変に対応できるようになりますよ^^
________________________________________
知識は使えてナンボ!【解剖学入門編無料】
⇓⇓⇓
https://utage-system.com/p/B1wVFfY3oESr/tDJVdMHi9s7S
________________________________________
【セラピスト養成スクールCEOL Academy JAPAN】
⇓⇓⇓どんなスクールかまずは知ってください。
________________________________________
【体験なんてもんじゃない!CEOLの30日チャレンジプログラムを無料で体験!】
⇓⇓⇓30日にあなたの可能性を一度かけてみてください!!絶対に人生が変わる!!